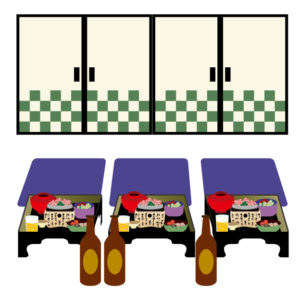不思議なもので、
子どもたちの絵とかピアノには、
どんなに下手でも「上手!天才!」とよく褒めるんですが、
小論文指導だけはマジになってしまいます。。。
目指すべき高いゴールを知っているだけに、
「課題文を読み間違えてるだろ、ゴルァ!」と言いたくなっちゃうんですね(笑)
何をどう教えても読めるようにならない子って、一定数いるんですよ。
能力の問題なのか、心理的な何かのブロックなのかわかりませんが。
そういう子に「出題意図を見抜いてベストな答案を書け!」と要求しても、無理なんですよね。
読むところでつまづいて、書く練習に入れません。
この場合はどこかで見切りをつけて
「出題意図とはズレてるけど、文章はちゃんと成立している」というセカンド・ベストをゴールにするのが現実的です。
出題意図で上位50%に入れなくても、下位50%の中で一番取ればチャンスは残ってますから。
という、理想と現実の折り合いのつけ方を
私も最近ようやく覚えてきたところでして。。。(苦笑)
<メルマガ【ミニマル思考カフェ】2021.1.27 Vol.0883>
関連動画
大学入試の小論文は「3段落構成×2パターン」を使い分けよう

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。