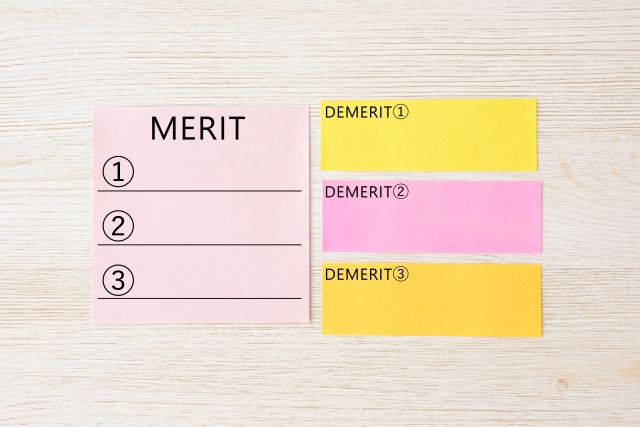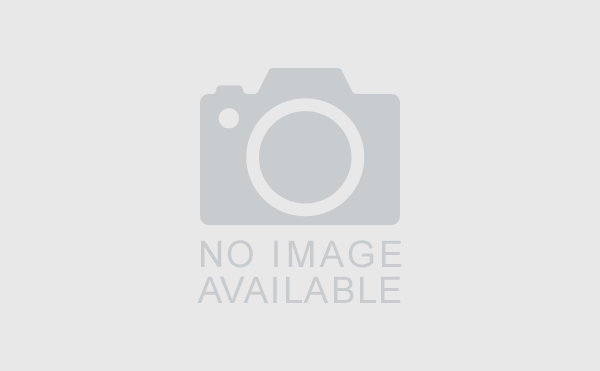朝日小学生新聞の連載「楽しく発表 プレゼンハッピー」がLINE NEWSに掲載されました。
小学生新聞の編集部はすごいですね。
子ども向けの文体に見事にリライトしてくれるんですよ。
今回掲載された記事と、元の原稿を比較してみましょう。
【元の原稿】
その場で思いつくままに話すと、次の内容を忘れてしまったり、話が脱線してしまったりしやすい。予定通りのプレゼンテーションをするには、前もって原稿やメモを用意しておこう。
ただし原稿を書くときには気をつけたいことがある。それは「話し言葉」と「書き言葉」の違い。高学年になるほど長い文章を書けるので、原稿の文も長くなりがち。でも「。」で終わるまでが長い文は目で読むには理解できても、耳で聞いたとき理解が難しくなる。
「◯◯は△△です。その理由は〜です」のように、短い文を並べて話すのがわかりやすいプレゼンのコツだ。
【紙面の完成版】
伝えたい内容を聞き手に正しく理解してもらうために欠かせないものって何かな。いくつかの要素を挙げられるけど、とくに大事なのが準備、すなわち原稿づくりだよ。プレゼンをしているとき、思いつくままに説明すると話が横道にそれたり、伝えるべき内容を忘れたりしがちだ。
原稿をまとめるときに「書き言葉」を使うと思うけど、ちょっと気をつけよう。書き言葉は一文が長くなりがち。目で追って読むときは理解できても、耳で聞くとわかりにくくなるんだ。「◯◯が△△なのは〜だからです」という文なら「◯◯は△△です」「理由は〜だからです」などと短めに分けてみよう。
ふんわり感が全然ちがいます。
声に出して読んだらテンポもまるで違う。
書き手の多くは「文体=単なる癖」だったりします。
それが読者にとってベストな文体かどうかはわからない。
リライトしてもらうことで、
初めて自分の文体を客観視することができました。
<メルマガ【ミニマル思考カフェ】2021.5.18 Vol.0994>

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。