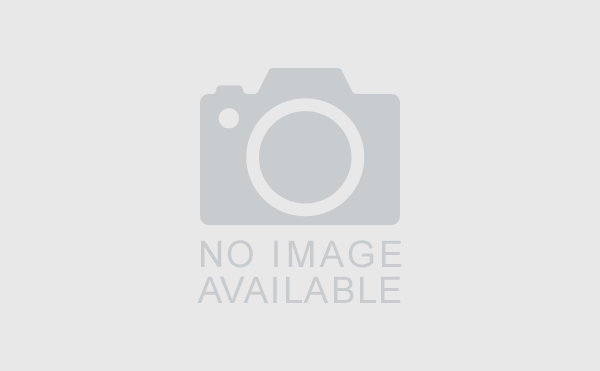すべらない話の構成「3D話法」とは?
私がセミナーでお伝えしているコンテンツの構成法に
「3D話法」というものがあります。
-300x225.jpg)
ざっくり要約すると、
文章でもプレゼンでも
- Difference(ライバル商品や従来の企画との差別化)
- Detail(スペックや導入事例など)
- Development(今後の展開)
この3つのベクトルで話を構成すると、読み手・聞き手は必ずどこかに食いつくというものです。
たとえば、新商品を紹介するときは
「この太陽電池、従来のものとは◯◯が違うんです(Defference)
それを可能にしたのがこの△△技術。NASAでも採用されています(Detail)
これが普及すると、日本のエネルギー事情がこんなに変わるんです(Development)」
Detailばかり詳しく語っても、相手は動いてくれません。
まずDefferenceで聞き手の興味を引いて、最後にDevelopmentで聞き手に希望を感じさせることで「刺さるプレゼン」になるわけです。
話し方の基本「PREP法」
一方、「話し方の基本」として「PREP法」というのがあります。
- Point(要点を最初に言う)
- Reason(その理由)
- Example(具体的事例)
- Point(要点をもう一度)
3D話法とは順番が、ベクトルが全然ちがいます。
どっちが正しいとかではなく、
1分で報告するときはPREP法、
時間をかけて相手を動かすときは3D話法
と使い分けるのが正解です。
「1時間の定例的な発表」は3D? それともPREP?
・・・という話をしたところ、受講者の方からご質問をいただきました。

「四半期に一度、1時間ほどの定例的な発表をします。
この場合はPREP法ですか? それとも3D話法ですか?」
定例的な会議で5分か10分の報告だけならPREP法でもいいでしょうが、
1時間ですからね。
PREP法で1時間もしゃべると、
「結論はもうわかった。あとはその理由が並ぶんだな。もういいや」
と、聞き手を引っ張るのが難しくなります。ネタバレしてますから。
定例的で、みんなが惰性になりそうな会議の発表こそ、
最初に「Difference(差別化)」を打ち出しましょう。
「今回はいつもと趣向を変えて、△△の観点からご報告します!」
「今期の業績の特徴を一言でまとめると、◯◯効果です!」
(お、何か面白いこと始まりそうだぞ)と思わせたら勝ちです。
冒頭で(はいはい、いつもと同じ話ね)と思われたら、
あとで大事な話をしてもスルーされてしまいますからね。

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。