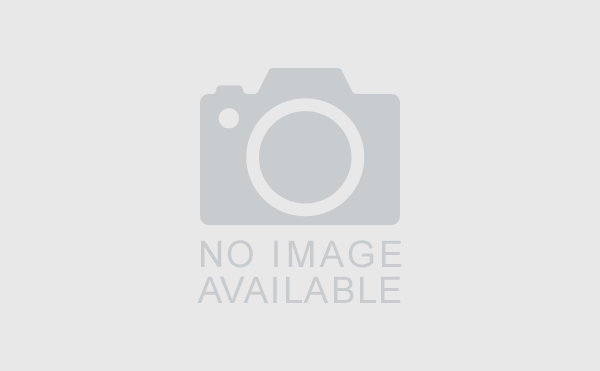学校の先生に「小論文をPREPで書け」っていわれたんだけど、PREPって何?

会社の研修でPREPを教わったけど、現場に戻ったらどう使えばいいのかわからない・・・
「PREP(プレップ)」。
ロジカルシンキング、ロジカルライティングでよく聞く割に、
「結局よくわからない」という人も多いですよね。
でも大丈夫!
この記事を読めば、「PREPって何?」という超基本から実際の文章を書くときの使い方までバッチリわかります。
《Contents》
PREPとは?
いわゆる「結論から話せ」
PREP(プレップ)という話し方・書き方の構成があります。
Point 最初に要点
Reason 次にその理由
Example そして具体例
Point 最後に要点をもう一度
この頭文字をとって「PREP」。
いわゆる「結論から話せ」というやつですね。
たとえば「高校生にアルバイトを許可すべきかどうか」というディベートなら
Point「私は高校生のアルバイトには賛成です」
Reason「なぜならビジネスを学ぶことができるからです」
Example「あのスティーブ・ジョブズも高校時代にHP社の工場でアルバイトをしていました」
Point「ゆえに私は高校生のアルバイトに賛成です」
こんな感じです。
PREP上達のカギは Reason と Example の区別
PREPが日本のビジネスパーソンにあまり普及しなかった原因の一つに、「ReasonとExampleの混同」があります。
Exampleを「根拠」と訳して教えられることが多かったため、「理由も根拠も、同じでしょ? なんで2つ並べるの?」と納得しにくいんですね。
Reasonは「理由」、Exampleは「事例」と覚えましょう。
さっきの例をもう一度出しますね。
Point「私は高校生のアルバイトには賛成です」
Reason「なぜならビジネスを学ぶことができるからです」
Example「あのスティーブ・ジョブズも高校時代にHP社の工場でアルバイトをしていました」
Point「ゆえに私は高校生のアルバイトに賛成です」
「ビジネスを学べる」というのは理屈です。一般論です。目に見えません。
これに対し、「あのスティーブ・ジョブズも」というのは実在する有名人の具体例です。目に見えます。
Reason(一般論)だけだと、「理屈としてはわかるけど、ホントなの?」と疑われます。
Example(事例)だけだと、「それはスティーブ・ジョブズが特別なんでしょ?」と反論されます。
一般論と個別の事例がセットだから説得力をもつわけです。
名探偵の推理も同じです。
Point「犯人は、あなただ!」
Reason「なぜなら、この密室にあの小窓から入れたのはあなた以外に考えられないからだ」(推理)
Example「その証拠に窓の内側からあなたの指紋だけが検出された」(証拠)
Point「ゆえに、犯人はあなただ!」
この場合も、
Reason(推理)だけだと「ハハハ、それはあなたの想像でしょ?」と言い逃れができてしまいます。
Example(証拠)だけだと「窓に触ったら人が死ぬとでも言うわけ?!」と逆ギレされます。
推理と証拠がセットになるから説得力をもつわけです。
小論文、論文でのPREPの使い方
結論から話すな?
この「PREP」、短いメールや報告書に応用するのはわかりやすいんですが、
セールストークや長めのプレゼンテーションの構成にそのまま使えるかというと、話は別です。
営業マンが初対面でいきなり「買ってください! なぜならば・・・」と切り出したら、お客様はドン引きしますよね。
「あなたのこの問題を解決してさしあげます」がお客様にとっての「要点」であって、
「そのためにこの商品を買ってください」は問題解決の手段にすぎないわけです。
PREP法は本来、
「1分間で報告するときの話し方」なんです。
「時間をかけて相手を動かすための話し方」とは別なんですよ。
同じように、
小論文や論文といった「試験の答案」も「時間をかけて採点者を動かすための文章」です。
PREPをそのまま「段落構成」にするのはおすすめしません。
小論文の構成、プレゼンの構成
大学入試の小論文、採用試験や昇進試験の論文の場合、一般的なのはこのような3段落構成です。
- まず問題となっている事実を共有する(問題提起)
- 次に、その原因を明らかにする(原因分析)
- 最後に、どうするべきかを提案する(解決策)
ただし、増税や原発再稼働など、世論が賛成/反対に割れるようなテーマの場合は、次のような3段落構成にしましょう。
- その施策の必要性(メリット)
- その施策の問題点(デメリット)
- メリットを活かしデメリットを抑えるアイデア(解決策)
プレゼンやセールストークなら
- まずこの商品やサービスが従来のものとどう違うのかを示し(差別化、Difference)
- その裏付けや導入事例などを詳しく説明し(具体的詳細、Detail)
- 提案をしたり未来を描いたりする(次への展開、Development)
これを私は「3D話法」と呼んでいますが、詳しいことはまた別の機会に。
いずれの構成も、「相手にしてほしい行動」は最後です。「結論から話せ」ではないんです。
PREPを日本に広めた外資系コンサル会社の人たちも
自分の部下には「PREPで報告しろ」というものの、
自分がクライアントにプレゼンをするときは3D話法だったりします(笑)
PREPは「全体の構成」ではなく「1段落の構成」
PREPを使うとしたら、上記の3段落それぞれをPREPで構成するといいですね。
たとえば上述の「問題提起/原因分析/解決策」の3段落構成なら、こんな感じです。
1 問題提起
Point「◯◯が問題である」
Reason「なぜならこういう人が被害に遭うからである」
Example「実際、こういう事件が報じられている」
Point「ゆえに◯◯に対処しなければならない」
2 原因分析
Point「なぜ◯◯は大事故につながるのか」
Reason「△△を抑える機能がないからだ」
Example「この事例でもそうだった」
Point「以上が◯◯で大事故になる理由である」
3 解決策
Point「したがって、ミスが小さいうちに発見できる仕組みが必要だ」
Reason「トラブルをゼロにはできないが小さくすることは可能だからだ」
Example「具体的には、こういう構造が考えられる」
Point「こうすればミスを早期発見して事故を防ぐことができる」
充実した内容になりそうです。
というか、この型で書かれた文章はめっちゃ読みやすいはずですね。
もちろん大学入試の小論文では
PREP以外の段落の埋め方もありますが、
一つの型として練習するのは悪くないと思います。
PREPは「文章全体の段落構成」ではなく「1段落の書き方」と覚えておきましょう。
〈メルマガ【論文アカデミー】2021.6.14 Vol.012〉
おすすめ書籍
PREPについてもっと詳しく学びたい方にはこちらの本がおすすめ。
1冊まるまるPREPに特化していて、わかりやすさはNo.1です。
すぐできる! 論理的な話し方 話の組み立て方が上手になるPREP法の使い方
大嶋友秀・著 日本能率協会マネジメントセンター
関連動画
3D話法についてはこちらの動画もどうぞ。
小論文の段落構成についてはこちらの動画で詳しく解説しています。

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。
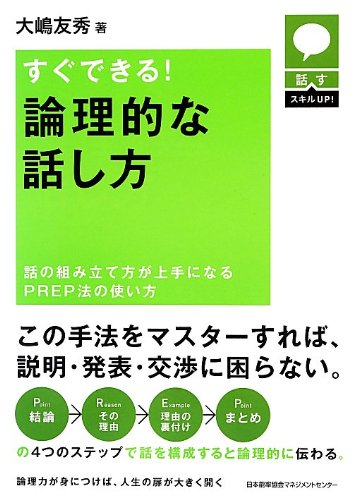

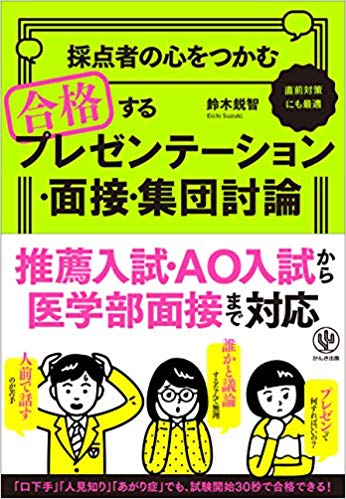

.jpg)