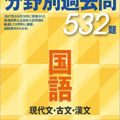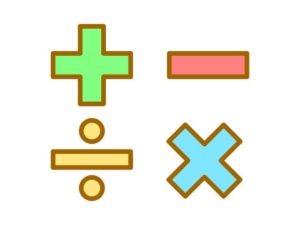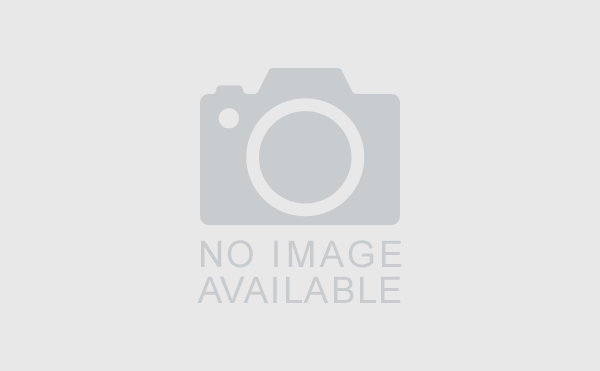答案の評価を「100点満点の点数制」にするか「ABC評価」にするかというのは難しいものです。
英語や数学のように生徒たちの実力が1点刻みに並ぶとか、
1点刻みで徐々に上がっていくという科目は点数制に向いているのですが、
小論文はどうなのか?
正しい日本語を書けているかどうかを見るなら、
100点満点から機械的に減点していけば学力順に並びそうです。
ところが資料や課題文の理解に重きを置くと、
普通の高校生が大学入試問題をやった場合、半数の答案が「論外」だったりするんですね(苦笑)
こうなると「0点」が続出してしまいます。
それに、細かく点数化するって手間もかかります。
面倒なので私はいつも「ABC」です。
CSS公務員セミナーでは
段落構成すら出来ていないものが「C」、
(講義動画を見ていないのがバレバレなので)
出題意図を外しているのが「B」、
出題意図を理解できたものは「A-、A、A+」。
「A-」になるのは問題解決がいまいちな答案です。「ポスターを張って啓蒙しよう」みたいな。
代ゼミ時代は
出題意図がわかっていないものが「C」、
(段落構成は書く前にヒントをあげていたので)
出題意図はわかっているけれど問題解決が凡庸なものを「B」にしていました。
この「ABC評価」、シンプルでいいのですが、
中には「ずーっとBからAに上がれない、達成感がない」という子も出てくるんですね。
そこで、代ゼミ時代に導入したのが「段位制」です。
答案の評価自体は「ABC」として、
それとは別に段位シールを貼りました。(金色の紙に勘亭流フォントで自作しました)
初段から二段、三段・・・と進み、
A評価1回で一段昇格、Bは2回で一段昇格。
凡庸なものを書いていても、地味に段位は上がるシステムです。
NHKの「ケータイ大喜利」を真似しました。
たしか七段の上に「レジェンド」を作った記憶があります。
子どもだましみたいですが、
浪人生も金色のシールもらうと喜ぶんですよ(笑)
評価をシンプルにして、生徒には達成感を与える。
「ABC評価+段位制」、おすすめです。
〈メルマガ【論文アカデミー】2021.4.19 Vol.002〉

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。