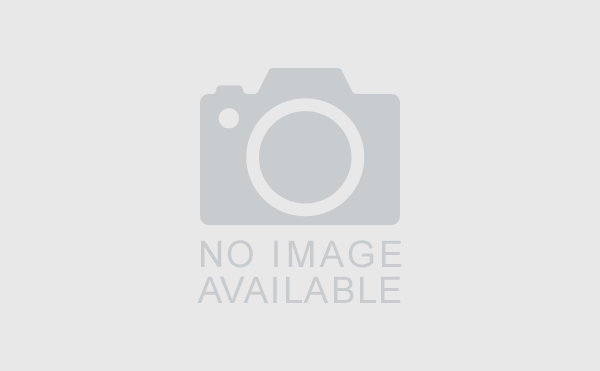私の参考書の著者プロフィールには必ずこう書いています。
「代々木ゼミナール講師時代、小論文を「文章表現ではなく問題解決能力のテスト」と再定義することによって合格率を倍増」
今日はこの「合格率倍増」の裏話をしたいと思います。
実は私、小論文の先生になるつもりはなかったんですよ。
英語の先生になろうと思って代ゼミの採用試験を受けに行ったら、
担当者が間違って私を国語枠にエントリーしていたんです(笑)
「これも天の声かな?」くらいのノリで現代文講師になりました。
2年後、今度は「小論文も教えてくれ」と言われました。
やったことねーよ。書いたこともねーよ。。。
しょうがないので、最初は樋口先生とか田村先生とかの有名どころの本を読んで、
恐る恐る教えてみるわけですが、
自分でも「何を書けばいいのか」がわかっていないので、教えようがないんですね。
無理やりそれっぽい「模範解答」的なものを書いて配っていましたが、
いま思えばすべて【ガッカリ答案】です。
(この年度は私の黒歴史・・・)
生徒の評判も散々で、100人いたクラスが7人になり(!)
アンケートでも現代文での高評価を小論文の低評価が打ち消してしまい・・・
代ゼミの年間コマ数も減らされて崖っぷちに立たされました。
追い詰められて、
当時金髪だった私もさすがに腹をくくります。
「小論文を一から研究し直そう」
まずは実際の入試問題を見るところから。(それすらしてないからダメだったんですがw)
当時、河合塾から全国の大学の小論文の問題を収録したボックスセットが発売されていて、
それを買って文系理系、国立私立を問わず大量の問題に目を通しました。
干された予備校講師は春休みが長いので。
すると気づくんですね。
小論文が求めているのは「個人的な主張」ではなく「世の中の問題を解決する方法」じゃないか?と。
そして2000年の新学期が始まりました。
「小論文は問題点を挙げて、解決策を書くんだよ」
教えたのはこれだけ。まだ段落構成とかのメソッドは未完成でした。
最初に反応したのが添削者(大学院生のバイト)たちです。
「鈴木先生のクラスだけ漢字や言葉遣いのミスが少ない」
言葉遣いの指導なんかしていないんですが、「何を書けばいいのか」というゴールが定まると表記ミスが減るんですね。
私の模範解答は・・・まだ【モヤモヤ答案】だったかな?
「講演会でPRしよう」とか書いてましたから(笑)
それでも、その年のクラスから「小論文で受かった」という生徒が私の知る範囲で15人くらい出たんですね。(実際は英語や数学との総合点で決まりますが、本人が社交辞令でも「小論文で受かりました!」と報告してくれた分です)
前年は1人でしたから(それもたぶん英語で稼いだから)、正しくは「合格数15倍」(笑)
ここから毎年、三段落構成をパターン化したり、設問のタイプごとに切り口を選んだり、
問題解決のルールを体系化したりと、一歩ずつ改善を重ねました。
2011年に出した「小論文のオキテ55」はその辺のノウハウが完成する手前くらいです。
だから初心者向けとしてはちょうどよかったのかもしれません。
「小論文=問題解決」に気づいてから12年も経っていましたね(汗)
もうちょっと早く進化できたんじゃないかという気もしますが。。。
〈メルマガ【論文アカデミー】2021.4.21 Vol.003〉

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。