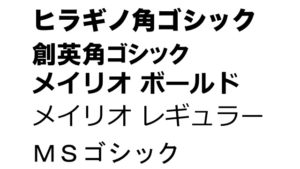問題点「満員電車が解消されない」
解決策「時差出勤するべきだ」
そうなんですよ。。。
おっしゃる通りなんです。
国も東京都も、すでに「時差出勤しましょう」と呼びかけてはいるんです。
ということは、この時点で「時差出勤すべき」という提案は
新しくもないし、効果もない
ということになってしまいますね。
問題解決のワークをやると
最初はみんな「月並みで効果のない解決策」を出してしまいます。
「『問題』がなぜ生じたのか」を考えてしまうからです。
それはそれで大事なんですが、
問い方をちょっと変えてみましょう。
「わかっちゃいるのに、できずにいるのはなぜか」
満員電車が問題なのではなく、
時差出勤できないことを問題とする。
問題の階層(レイヤー)を変えるんです。
では、なぜ時差出勤という制度が普及しないのか?
「相手のある業務だから」かもしれません。
それなら「相手のいない業務」の人は時間差オッケーなはずです。
「早く出勤しても、残業を早く抜けられるわけじゃないから」
残業代の管理が雑な会社ですね。そっちを先に直す必要があります。
「子どもを学校に送り出す時間は決まっているから」
そこは会社側では動かせないので、子どもの世話がいらない人を対象にしましょう。
「冬は早朝出勤が辛いから」
何も年間通して早朝出勤を続けなくてもいいですよね。冬は遅番、夏は早番でもいいでしょう。
ほら、話が現実的な方向に広がっていきます。
「なぜ問題が生じたのか」ではなく
「なぜ解決策を実行できずにいるのか」を考える。
アイデアに詰まったら、問い方を変えてみましょう。

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。