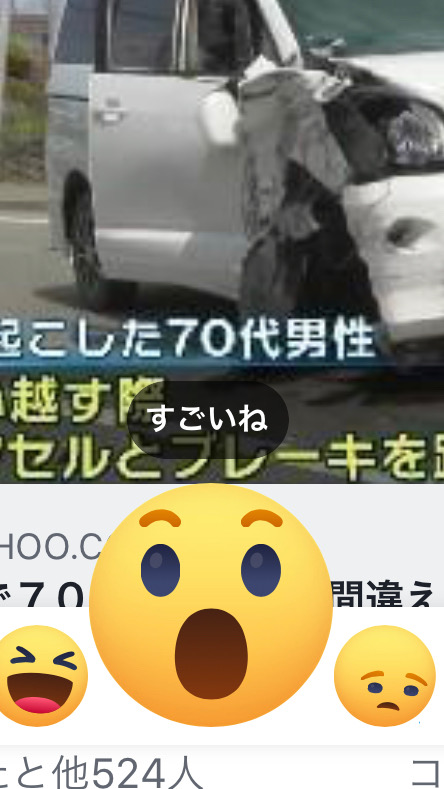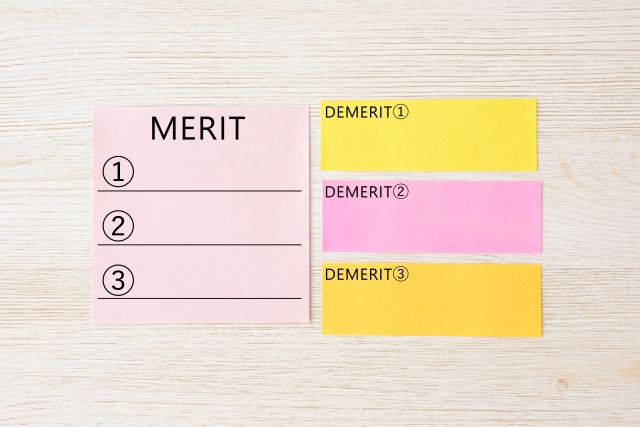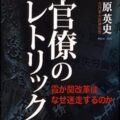人の話というのは、
聞いたときにはピンとこなくても
10年くらい経って初めて分かることもありまして。。。
速読教室の寺田昌嗣さんのセミナーに参加したとき、
「『べき』は無責任の助動詞」というお話になりました。
正直、そのときは意味がわからなくてですね、
それでも代ゼミの国語講師だった私に「専門家」として話が振られるわけですよ。
「って、教えますよね? 鋭智さん」
(教えますよね?って、そんなの聞いたことないし、教えたことないよ)
「え? ん? あ、そうっすね。ハハハ(汗)」
みたいな感じでお茶を濁しました。
小論文を「文章表現ではなく問題解決の科目だ」と再定義して
「解決策のアイデアを出さない答案には価値がない」と言い切っている私としては、
小論文の答案の最後は「~するべきだ」で終わるのが正しいわけです。
物事を論評するだけとか、既存の知識を並べただけの答案こそ、
社会の問題にコミットしていない「無責任な答案」じゃないかと。
(当時、世の中の「模範解答」の大半がこの「無責任答案」でした)
「~するべきだ」という提言は反対派の抵抗にあうかもしれないし、
新しいアイデアほど、現実的には間違っている(上手くいかない)可能性もあります。
でも、そんなリスクを取ってでも誰かがアイデアを出さないと物事は進みません。解決しません。
だから私の中での序列は
「~するべきだ」(提案)>「~である」(うんちく)
だったわけです。
ところが、あれから10年経って、
やっと、やっと
「『べき』は無責任」の意味がわかりました(笑)
この10年のあいだ、
潰れかかった予備校の中で改革案を出してはスルーされ、
また出しては骨抜きにされ、
またまた出したころには・・・手遅れでした。
ここまでは「~するべきだ」という提言をする側だったんです。
それから著者になり、いろんな場に登壇するようになり、
いろんな人のいろんな企画やビジネスに関わって
「~するべきだ」「~を変えてください」「絶対うまくいきますよ」
と、提言を聞く側に立つことが増えてきました。
すると、思うわけですよ。
「それ、上手くいくんかね?」
ナイスな思いつきも、組織がそれを採用して実現するとなったら
コストがかかります。人にも動いてもらいます。従来の仕組みを変えなきゃいけないこともあります。
で、もし失敗した場合、
誰が後始末するの? 元に戻せるの?
って話が残るわけですよ。
下からの提言が上に潰される一番の理由はこれだったかあ。。。
「上層部の頭が固いから」ではなく「組織にギャンブルさせるから」。
提言される側に立って初めてわかりました(笑)
だとしたら、アイデアを採用してもらうためには
「きっと上手くいくはず」ではなく
「すでに上手くいきました」というエビデンスを出すのが一番。
上に提言する前に、自分の裁量の範囲内で実験すればいいんですよ。
こう考えると、序列が変わります。
「~してみました」(実験結果)>「~するべきだ」(提言)>「~である」(うんちく)
「『べき』は無責任の助動詞」って、こういうことだったんですね!
いや~、ここまで理解するのに人生ずいぶん遠回りしたなあ!!
寺田さん、ありがとうございました!(10年越しのお礼)
あなたの人生を変える(かもしれない)寺田昌嗣さんの速読教室はこちらです。

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。