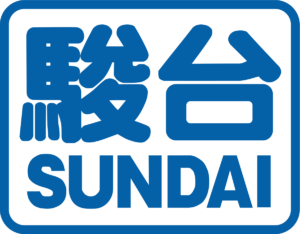「読解力って、どうすれば伸びるんでしょう?」というご相談、よくいただきます。
たくさん読めばいい?
現代文の問題を解けばいい?
読解力には3つの段階があるんですよ。
1 書いてあることを見落とさない。
2 書いてあることを別の表現に言い換えられる。
3 書いていないことを補完できる。
「書いてあることを見落とさない」というのは当たり前ですが、
書いてあることが目に入っても、「それが何なのかイメージできた」のと「文字として目に入っただけ」というのでは全然違います。
漢字の並んだ用語、文学的な比喩表現、耳新しいカタカナ語・・・わかったようでわかっていない言葉って多いですからね。
「具体的には誰が何することか」という例を正しく言えたら、ちゃんと理解できたことになります。
もう一つ重要なのが「書いていないことを補完する」。
筆者は当たり前すぎることは省略して話を進めます。
たとえば「グローバルな時代になると政治の求心力が低下する」。
なぜ?
ここには「グローバル→関税とか国際規格とか→一国だけで物事を決められない→決められない政治になる」という因果関係が省略されています。
これを頭の中で補完できた人と、よくわからんけど書いてある結論だけ鵜呑みにする人に分かれるわけです。
「言い換える」と「補完」って、国語のテストで問いにくいんですよね。
回答者の表現がバラバラになるので機械的な採点ができないからです。
そのため、現代文のテストでは「傍線部『◯◯』とはどういうことか=同じこと書いてある部分を探せ」という設問がメインになるわけです。
「ほら、◯ページの△行目に書いてあるじゃないか」と白黒つけやすいですからね(ほぼ視力検査ですが)
以上が、現代文の入試問題をやるだけでは「読解力」が思ったほど伸びない理由です。
読解力を伸ばそうと思ったら「言い換え」と「補完」の練習が必要です。
<メルマガ【ミニマル思考カフェ】2021.10.13 Vol.1142>

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。