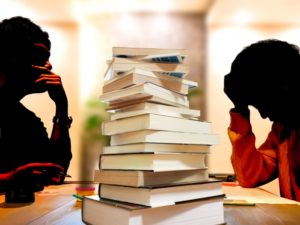代ゼミ時代、講師の待遇を決める大きな要素に
生徒によるアンケートがありました。
「授業はわかりやすいか」
「講師に親しみを感じるか」
「講師に熱意を感じるか」など、
いくつかの項目を5段階で評価するものです。
ただ、この方式には問題があって、
人気の度合いはわかるものの、
その授業に「効果」があるかどうかはわからないんですよね。
一方、
人気投票ではなく合格率を評価しようとすると、
またちょっと問題が。
一般入試は英数国社理の合計点で決まるため、
どの講師がどれくらい貢献したのか、わかりにくいんです。
(その点、小論文は単独で課す大学が多く、貢献度がわかりやすい唯一の科目でした)
しかも元々得意だった科目なのか、講師によって伸びた科目なのかを区別する必要もあります。
「成果」で講師を評価するのって、複雑で難しいんですよ。
いま思えば、
アンケートなんて1問でよかったんですけどね。
受験が終わってから、
「この授業は合格の役に立ちましたか?」
企業の研修担当の方とも「研修の成果をどう測るか」がよく話題になるのですが、
受講後のアンケートよりも、
たとえば「1年後」とか「資格試験の後」とかに
「この研修は◯◯の役に立ちましたか?」
と聞いてみるのが一番手っ取り早いかもしれません。

シリーズ累計25万部のベストセラー参考書「何を書けばいいかわからない人のための 小論文のオキテ55」の著者。代々木ゼミナール小論文講師を経て、現在は文章力トレーニングの専門家として大手企業の社員研修に多数登壇。合同会社ロジカルライティング研究室代表。