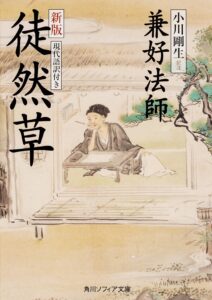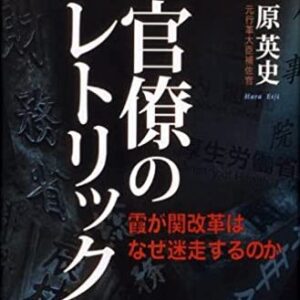いわき地区国語教育研究会のお招きで、先生向けのオンライン講演会に登壇しました。
テーマは「ビジネス国語とロジカルシンキング」。
学校で教わる国語とビジネスの現場で必要とされる国語力、この2つは本来合致しているはずなのに、現状は・・・というお話をしました。
たとえば「疑問形」。
社内の会議で、先輩のプレゼンに対して新人社員が質問をしました。
新人「いまの発表には根拠となるデータってあるんですか?」
先輩「おまえ、俺の発表にケチつけるのか?!」
新人(え〜、興味あるから聞いただけなのに・・・)
疑問形には用法が2つあります。
1 質問(答えや説明を求める)
2 反語(否定する意図)
上の例の場合、純粋に「質問」しただけなのに、相手には「反語」と受け取られてしまったわけです。
このように人間関係の地雷ともいえる危険なワード、反語ですが、
学校で習うのはこんな場面なんですよね。
徒然草 一三七
「花は盛りに、月は隈(くま)なきをのみ見るものかは」
[訳] 桜の花は満開のときに、月はかげりのない満月のときにだけ見るものであろうか(いや、そうではない)。
高校生のほとんどは疑問形の反語用法を「古文の訳し方のテクニック」として覚えます。
「これ知らないと、社会に出てから地雷踏むよ!」と教えてくれれば犠牲者が減るのに。
「ここテストに出るよ!」より大事だと思います。
こんな内容を90分お話ししました。
本来なら会場の写真とかアップするところなんでしょうけど、
オンラインなので会場写真がない!(苦笑)

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。