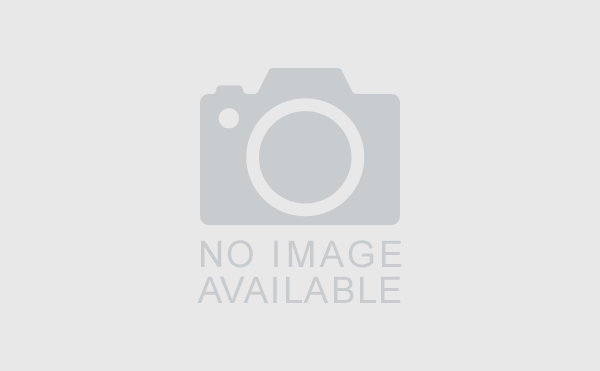こんなリクエストをいただきました。
「芸術には規則がなくてもよいか。(800字程度)」
大阪教育大学の美術コースの問題です。
この「規則」というのは解釈が2通りできそうですね。
1つは「人を不快にする表現はNG」のような社会的ルール。
もう1つは遠近法や黄金比、対位法のような表現上の法則性。
いずれにしても、これらと対比されるのは
「芸術は爆発だ!」ですかね。
芸術に規則が必要なのか、自由であるべきかというのは
一般市民からするとどっちでもいいんですが(笑)、
教育大学の美術専攻です。アーティストではなく美術の先生を育てる学科です。
抽象的な芸術論とか個人的な価値観に走らず、
「学校の美術教育の方向性」という現実的な話をしましょう。
段落構成は「メリット・デメリット型(ディベート型)」。
各段落250字を目安にすると250×3=750でちょうどいいでしょう。
各段落を更に2つのポイントに分けると、125×6=750。ツイッターで6回つぶやくのと同じです。
第1段落 美術教師がルールや法則を教える必要性
・社会的ルールの話
・遠近法などの法則性の話
第2段落 生徒に自由な表現をさせる必要性
・規則に縛られるとつまらない
・規則を破った芸術家の例
第3段落 学校の美術教師はどう教えるべきか
・ルールと自由のバランス
・すると美術の授業はどう変わるか
【解答例】
芸術作品には社会的なルールと作品自体の法則性という「規則」が存在する。表現の自由が認められているとはいえ、他人を不快にしたり人々に悪影響を及ぼすような作品は公開を認められないなどの制限を与えられるのが一般的である。また絵画であれば遠近法や黄金比、音楽であれば対位法など、昔から優れた芸術作品には法則性の裏付けがある。いずれにせよ生徒に芸術表現を教えるとき、これらの社会的ルールと作品の法則性を教えることにより、失敗や試行錯誤をせず最短距離で「評価される作品」を作ることができると考えられる。
一方で、ルールや法則性には自由な表現を妨げるというマイナス面もある。批判されないようにと社会的ルールの中で収めようとしたものは「無難な作品」になり、自分のアイデアや表現欲ではなく法則性を優先させたものは「凡庸な作品」になりがちである。キュビズムを確立したピカソやギターの新しい奏法を編み出したジミ・ヘンドリックスなど、歴史に名を残した芸術家は既存のルールや法則を覆すことによって新しい価値を生み出している。したがって美術教師には生徒の自由な発想や表現欲を認めることも求められる。
以上より学校における美術教育では、ルールや法則性を教えることと生徒の自由な発想や表現を認めることのバランスが重要になると考えられる。まずは自由な表現を引き出した上で、上手くまとめられない生徒には技術として法則性を教え、不快な表現をする生徒には社会的ルールを教えるべきである。規則をあとから教えることによって、規則に縛られるのではなく規則を表現の一手段として使いこなすことができるようになる。これによって美術の授業で描かれる生徒の作品も、お手本通りの画一的なものではなく、個性あふれるものになると考えられる。
(737字)
ジミヘンが芸術家の例に適切かどうかはわかりませんが(笑)
〈メルマガ【論文アカデミー】2021.6.7 Vol.011〉

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。