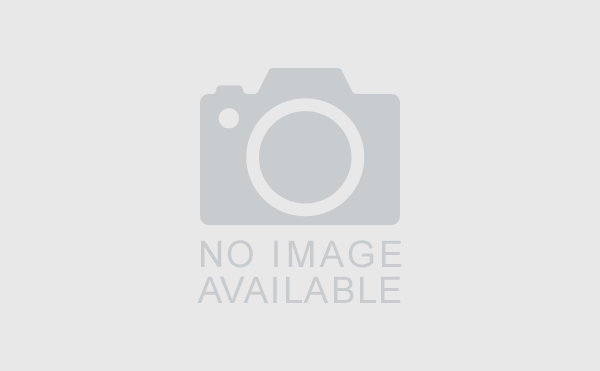小論文の段落構成については、
「3段落構成×2パターン」と教えています。
増税すべきか否かなど、「賛成/反対に世論が割れるテーマ」のときは
第1段落 メリット(or 自分の立場)
第2段落 デメリット(or 逆の立場)
第3段落 解決策(両者の折り合いをつける)
想定を超える災害が増えているなど、「誰が見ても問題であるテーマ」のときは
第1段落 問題提起
第2段落 原因分析
第3段落 解決策
以上の2パターンを正しく選択できれば、
どんな入試問題にも対応できます。
はい。「どんな問題にも」と言い切っちゃいました(笑)
根拠はあるんですよ。
「議論」にはディベートとディスカッションがあります。
ディベートというのは賛成/反対の2グループに分かれて意見を戦わせること。だから「賛成/反対に割れるテーマ」が選ばれます。
ディスカッションというのはグループに分かれずみんなで意見を出し合うこと。この場合は「誰が見ても問題であるテーマ」が選ばれます。
なので上記の段落構成2パターンというのは
「ディベート型」と「ディスカッション型」ともいえますね。
受験テクニックではなく、議論というものの構造です。普遍的な話です。
だから「どんな問題でも」と言い切れる(キリッ)
「どういう段落構成で書けばいいかわかりません」というときは
課題文と設問が「賛成/反対に割れている」のか「誰が見ても問題」なのかを理解していないときです。
さらっとキーワードだか拾い読みしてはいけないんですよ。
忙しいときに生徒が過去問持ってきたりすると、ざっと流し読みしたくなります。
でも、これだと何が問われているのかわからず、かえって時間を浪費してしまうんですね。
わからないときほど、課題文と設問をちゃんと読みましょう。
「この問題はディベート型かディスカッション型か」を意識して読めば、意外とあっさり糸口が見つかるものです。
〈メルマガ【論文アカデミー】2021.5.31 Vol.010〉

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。