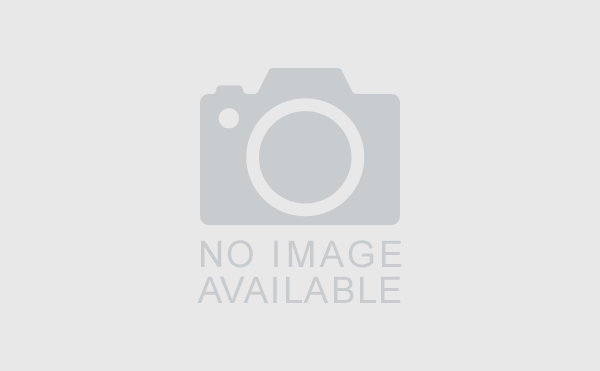「小論文の答案に『調べた知識』を書くんじゃないよ」
と生徒には教えていますが、
教える側が物知りになっておくことは必要です。
知識そのものが必要ということではなく、
いろんな角度から物を見るためにです。
予備校講師って、偏った発言を自由にできるんですよ。
昔は学生運動あがりの左翼バリバリの先生が思想を語っていました。
いまでも「◯◯は善、△△は悪」とか「こういう人間は嫌い」といって「世の中をぶった斬る」先生は珍しくありませんし、それがまた生徒にウケる。
私も新人講師のころはそんな感じでした。自分の価値観で白黒つけていました。
ところが、
小論文で出題される原発とか脳死移植とかテロリズムとか、いろんなテーマを調べていくと
物事にはメリットもデメリットもあって、世の中にはいろんな利害関係の人がいることがわかってくるんですね。
教壇から一刀両断できるほど世の中は単純じゃなかった。
それ以来、何を見聞きしても「別の立場の人もいるよなあ」と考えられるようになりました。
小論文を教え始めたのは成り行きですが、おかげでちょっと大人になれたかもしれません。
「どうしたら思考力を伸ばせますか?」
と聞かれて、私も答えに窮することがよくあるんですが、
私自身も「思考力を伸ばした」わけではなく
「いろんなテーマを勉強した」だけと言った方が正確です。
1つのテーマで何冊も本を読んだり、現地に行ったり、当事者に会ったりしました。
視点を増やすという意味では、
生徒に広く知識をつけさせるのは正しいアプローチといえます。
ただし、あくまでも目的は「書くネタとしてではなく、視点を増やすため」であることを
教える側が理解しておくことが必要です。
〈メルマガ【論文アカデミー】2021.5.8 Vol.007〉

シリーズ累計25万部のベストセラー参考書「何を書けばいいかわからない人のための 小論文のオキテ55」の著者。代々木ゼミナール小論文講師を経て、現在は文章力トレーニングの専門家として大手企業の社員研修に多数登壇。合同会社ロジカルライティング研究室代表。