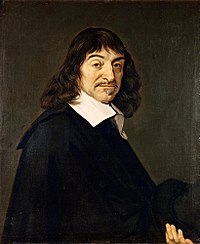【救急車の救急出動件数と搬送人員の推移】
小論文の問題です。
「このグラフを見て、考えたことを述べよ」
まず資料の解釈が2通りに分かれます。
「出動件数も搬送人数も倍以上に増えた!」という解釈と
「1割は空振りしてるじゃないか!」という解釈。
そうなんです。出動回数よりも搬送人数の方が少ないんです。
50万回は「出動したけれど、誰も運ばなかった」ということになります。
その分、本来必要な人を搬送するのが遅れている可能性がありますね。
そこで「無駄な出動を減らす方法を考えろ」というのが出題意図です。
「イタズラ電話の番号をブラックリストに入れる」
飲食店や旅館のドタキャンならブラックリストでいいでしょうが、
救急車の場合、オオカミ少年みたいに「今回は本当だったのに・・・バタッ」という事態もあり得ます。
「救急車を呼ぶほどかどうかわからない人のための相談窓口を作る」
すでにあるんですよ。「#7119」というものが。
総務省消防庁「救急安心センター事業(#7119)ってナニ?」
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate007.html
でも、ぶっちゃけ「#7119」なんて周知されていないし(覚えにくい)、
「赤ちゃんが39度!大変だ!」と大慌ての人が
「まずは救急安心センターに電話してみよう」なんて冷静に判断するとは思えません。
119番に「通報する人」をどうにかしようとしても、限界がありそうです。
ならば見方を変えましょう。
通報を「受ける人」は、なぜその通報が「いたずら」とか「大げさ」と判断できないのか?
声だけだからじゃないですかね?
だとしたら、
「119番をテレビ電話にする」
という発想になります。
実際、すでに「試み」はあるんですが
「119番通報をスマホからビデオ通話で、日立が消防向けに販売」
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1086212.html
こういう最先端の情報を「知っているかどうか」は重要ではありません。
「悪い人の心を変える」ではなく
「いい人でもついやってしまう仕組み」に原因を求めることで
最先端の現場と同じ解決策にたどり着く
という思考のプロセスが大事なんです。
<メルマガ【ミニマル思考カフェ】2020.2.9 Vol.0530>

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。