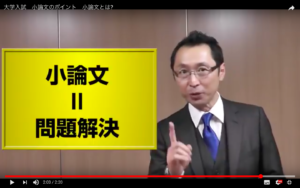ある高校に講演会でお邪魔したときのことです。
応対してくれたのは笑顔の素敵な女性の先生。
応接室でアイスコーヒーを出していただき、「では、そろそろ会場へ」とにこやかに案内されたのですが・・・
校内はちょうど授業が終わったあと。講演会は3年生対象なので、1、2年生は掃除の時間になります。
ま、どこの学校も一番騒がしい時間帯ですよね。ほうきを振り回してふざけている男子とか、クネクネしておしゃべりに興じる女子とか、懐かしいです。
すると、さっきまでニコニコしていた女性教諭の顔が一変しました。
「こら!そこ!おしゃべりしないっ!」
「そこ!ふざけないで掃除するっ!」
「キーーーーーーーーッ!」
見る生徒、見る生徒、全員を叱り飛ばすその後姿には、さっきまでの笑顔の面影はありません。
そのギャップにドン引きしながら後ろを歩いていると、
体育館の入口で振り返り、満面の笑顔で
「こちらです。どうぞ♪」
どっちが彼女の本当の表情なのか、わかりません(笑)
そういえば学校というのはこんな感じだったなあという懐かしさもありますが、
「叱る/叱られる」という文化に属していない私のような人間の目にはかなり異様な光景に映りました。
そうです。世の中には「叱る/叱られる」という文化で生きている人とそうでない人がいるのです。
管理職向けの企業研修では「叱り方研修」というのもあって、「部下を成長させる叱り方」「パワハラにならない叱り方」などを教えてくれるものです。
でも、これは学校とか正社員のサラリーマンとかの「タテ社会」特有の文化。
叱ることで下の人間を育ててやろうという、上下関係がはっきりした世界の文化です。
近年のようにアウトソーシングが増えてくると、この「上下関係」が変わってきます。
発注する企業と受注する企業・個人は本来「対等の関係」です。
発注元は自分たちではできない業務を外部に委託するわけですから。
誰かにお金を払ってお願いしないと、困るわけですから。
ちなみに予備校講師の多くも個人事業主として予備校から業務委託を受けている形です。
だから条件が合わなければ次年度の契約を更新せず、ライバル予備校に移籍するのもルール上はOK。
その代わり、予備校は講師を育ててはくれません。
「うちはプロとして依頼しているんだから、スキルアップしたければ自分でやれ」
私が代ゼミの講師になったとき、役員から最初に言われた言葉です。
それ以来、講座やセミナーに通って勉強するのは全額自腹。もちろん個人事業主なので経費で落としますが。
ここには「叱って育てる」といった関係性はありません。
何か至らない点があれば「こうしてくれ、これはするな」と言われますが、
それは要望、リクエストに過ぎません。こちらとしてはリクエストに応えるだけです。
要望に応えない、応えられないという場合も、叱ってはくれません。
次から仕事の依頼がなくなるだけです。他の人に仕事が回るだけです。
そんなドライな世界で生きてきたので、「大人が他人を叱る」という光景をたまに見るとびっくりしてしまうわけです。
「プロ」「業務委託」「外注さん」「下請け業者」「非正規雇用」……呼び名はいろいろありますが、
発注元の企業と「対等の契約関係」であることは共通です。
外部の取引先である以上、「叱って育てる」なんておこがましいことはできません。
要望・リクエストを出すか、仕事の依頼をやめるか、それだけです。
では正社員のサラリーマンの世界ではこの先も「叱る/叱られる」の文化が続くのでしょうか?
おそらく変わってくるでしょう。
従来、サラリーマンの「叱って育てる」文化には「叱られて成長したら会社の幹部になれる」という前提がありました。
だから叱ってでも成長させないと会社が困るし、叱られる社員も我慢すればいずれ報われたわけです。
でも現在、「叱られて成長したら会社の幹部にしてあげる」と保証できる日本の企業がどれだけあるでしょう?
会社も保証はできない、社員も会社を頼りにはできない。
正社員と会社の関係も「一時的な契約関係」になりつつあります。
そうだとしたら、明日には他人になるかもしれない上司に叱られるのは割に合いません。
割に合わないものは我慢もしにくいでしょう。
パワハラが訴訟沙汰になる、上司のプレッシャーで心を病む社員が多発する、新入社員がすぐ辞める……その背景には、こうした構造の変化もあるのです。
毎日「叱っている」みなさん、ビジネスの場で感情をぶつけても得なことはありません。
クールに要望、リクエストを伝えましょう。
毎日「叱られている」みなさん、「取引先」にすぎない上司のために心を病むのは割に合いません。
相手の言葉から「感情」と「用件」を分けて、さっさとリクエストにだけ応えましょう。
もう「叱る/叱られる」という時代ではないのです。

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。