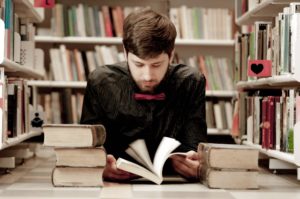
執筆中の本の企画に関連して、ときどき大学生を相手に実験をしています。
よくある「本文の内容として、正しいものを選べ」という選択問題。
公務員試験で出される文章は600〜1000字程度。大学入試センター試験の3000字前後に比べるとかなり短いです。
この問題を、「まず本文を読んで、それから選択肢を見て選ぶ」という(普通の)手順で解かせると、
早い学生で3分、大多数の学生が6分以上、遅い学生は10分過ぎても答えが出ないという状態。
そして正答率は……
大学のいわゆる「偏差値」にかなり比例しますが、解くスピードと正答率には相関がありません。
「わかったから速い」と「雑だから速い」、「わからないから遅い」と「ゆっくり読めばわかる」が混在しているようです。
次に「先に選択肢を見て、『間違いが仕掛けられていそうな部分』を探して線を引き、それから本文に目を通す」という逆の手順で解かせてみると、
早い学生で2分、遅い学生も10分以内には全員解き終わります。
そして正答率は……
大学の偏差値に関係なく8割を超えます。
(もっとも、ただ「選択肢を先に見ろ」と言うわけではなく、「間違いが仕掛けられていそうな部分」の探し方についてのレクチャーはするのですが)
どうやら「書いてあることを受け入る」よりも「◯◯についての答えを探す」方が圧倒的に速く、正確に読むことができるようです。
本を読むのが得意な人、苦手な人の根本的な違いはここにあるのかもしれません。
読書好きな人というのは、何か「知りたい」という欲求があって本を手に取るもの。
しかも読み進めるうちに「では、これはどうなんだろう?」と次の疑問が浮かび、その答えを見つけては「じゃあ、これは?」と「問い→答え→問い→答え」の連鎖に入っているものです。
これに対して他人から「読め」と興味のない本を渡されても、そこに書いてあることは何の「答え」でもありません。
だから内容を「自分の知っている例」に結びつけてイメージしたり、「従来の常識」と対比させたりという理解のしかたができないのです。
「読むのが遅い、苦手」という人は「読む技術」以前に自分の「興味、関心」を解放するのが先かもしれません。
ちなみに、公務員試験では「文章整序(意味が通るように段落を並べ替える)問題」というのも出題されます。
これも、接続詞や指示語に従って「並べ替えよう」とすると、ドツボにはまって1問10分かかる受験生もいるのですが、
「キーワードを見つけて、全体を◯◯と△△に分ける」という解き方だと
最短で1問45秒という学生がいました。
やはり「受け入れる」より「探す」方が効率的なようです。

合同会社ロジカルライティング研究室 代表
ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者
就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。
現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。
「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。

