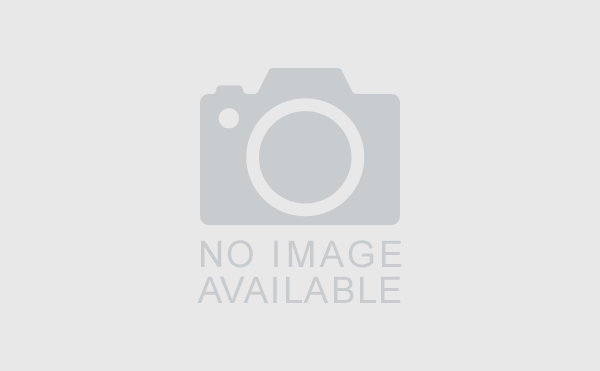小論文を教えていて、一番ガックリするのが
1200文字びっしり書いているのに、
課題文の理解がズレているので内容が的外れ・・・
という答案ですね。
いっぱい書いた努力が見えるだけに、全否定するのも心苦しい。
かといって、これでOKを出してしまうと本人のためにならない気がする・・・。
書く練習が先か読む練習が先かという問題が悩ましいのは
その生徒がどこまで伸びる子か予想つかないからです。
順調に読解力がつくのなら「読む→要約→書く」の順番で教えていいんですが、
やってもやっても読解力がつかない子って一定数いるんですよね。
学力的に読解力がない子の場合、
私は「書ければいいや」と切り替えます。
おそらく難関大学にトップで合格しようという感じではないでしょうから。
読めてなくても書ければ受かる大学もたくさんあります。
一方で、
一見優等生風で、文章力はあるのに読み方がいつもズレているという子もいます。
先入観あるいは常識が強いのかもしれません。
このタイプは公務員試験の論文には強いんですが、
大学入試の小論文では引っかかるんですね。
大学教授は常識を批判する視点の文章をよく選ぶので。
私だったら、
こういう子には課題文型の小論文をやらせる前に
グラフ問題を出しますね。
私の本によく出てくるエイズや結核のグラフのように、解釈が2つに割れる問題です。
文章を読む前に、「物事には別な見方もある」ということを教えるわけです。
それをクリアしたあとで課題文を要約する練習に入ると、
少なくとも「解釈が違う」ということに納得しやすくなるようです。
読解力のない子にはグラフ問題。
私の小論文の本で必ずグラフ問題を扱っている理由でもあります。
〈メルマガ【論文アカデミー】2021.4.13 Vol.001〉

シリーズ累計25万部のベストセラー参考書「何を書けばいいかわからない人のための 小論文のオキテ55」の著者。代々木ゼミナール小論文講師を経て、現在は文章力トレーニングの専門家として大手企業の社員研修に多数登壇。合同会社ロジカルライティング研究室代表。